はじめに:小1の壁ってなに?
「小1の壁」という言葉を聞いたことがありますか?
この言葉は、子どもが小学校に入学した後、親が感じるさまざまな戸惑いや不安、生活の変化を表しています。
保育園や幼稚園の頃とは違い、急に“自立”を求められる場面が増え、親のサポートの形も大きく変わります。
「朝の支度が間に合わない」「宿題はどうサポートすればいい?」「学校での様子が見えにくくて心配…」
そんな気持ちを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「小1の壁」で悩む親御さんに向けて、よくある不安とその対処法を、やさしい視点でお伝えします。
小1の壁で親が感じやすい不安とは?
朝の支度が間に合わない
保育園時代と比べ、小学校は登校時間が早くなります。
子どもに時間感覚がまだなく、朝の支度に時間がかかることも多いですよね。
「早く!」「もう時間だよ!」とつい声を荒げてしまい、自己嫌悪に陥ることも……。
学校での様子が見えにくい
入学後、保護者の学校との関わりは少なくなり、子どもの一日の様子が分かりづらくなります。
「友だちはできたかな?」「先生とはうまくいってる?」と心配が尽きません。
放課後の過ごし方が変わる
学童保育に預ける方もいれば、家でひとりの時間が増える子もいます。
どちらのケースでも、「安全に過ごせているか」「さみしくないか」と不安になるものです。
家庭学習にどう向き合えばいいの?
宿題や音読など、「家庭学習」がいきなり始まるのも小1の大きな変化。
「ちゃんと見てあげられるかな?」「教え方、これで合ってる?」と悩む声も多く聞かれます。
子どもに起きやすい変化とサイン
帰宅後すぐに寝てしまう
学校生活では、新しい人間関係、授業、ルール…。子どもにとっては、毎日がフルマラソンのようなもの。
帰ってきたらぐったり、夕飯も食べずに寝てしまうことも珍しくありません。
話しかけても反応が薄い
疲れや緊張が続くと、家での受け答えがそっけなくなる子もいます。
「今日はどうだった?」と聞いても「ふつう」としか返ってこない…そんな日もあるでしょう。
イライラしたり泣きやすくなる
いつもは元気な子が、突然泣いたり怒ったりすることも。
これは、がんばっているからこその“心の疲れ”かもしれません。
親ができる5つのサポート方法(詳しく解説)
① 完璧を求めない
子どもにも、親自身にも「完璧じゃなくていいよ」と伝えてあげましょう。
入学すると、「宿題をちゃんとやらなきゃ」「忘れ物をさせちゃダメ」など、親の側もつい気を張ってしまいがちです。
でも、小1はまだまだ“練習期間”です。忘れ物も失敗も「学びのチャンス」。
たとえば、忘れ物をしてしまったときも
「今度はどうすれば忘れないかな?」と一緒に考えることで、自立への一歩になります。
そして、親自身も「今日はイライラしてしまったな…」という日があっても大丈夫。
子育てに“満点”はありません。子どもと一緒に成長していく姿勢を大切にしましょう。
② 生活リズムを整える
“がんばらなくてもスムーズに回る毎日”をつくるのがカギです。
朝がバタバタしてしまう…というのは多くの家庭で共通の悩み。
でも、ちょっとした工夫で親も子もラクになることがあります。
- 前の晩に持ち物をそろえておく
- 起床後すぐにテレビやスマホをつけない
- お支度チェック表を作って、子どもが自分で進められるようにする
また、夜はできるだけ同じ時間に寝ることを習慣にすると、朝のリズムも整いやすくなります。
睡眠・食事・運動の3つのバランスが、子どもの安定した学校生活を支える大きな土台になります。
③ 短い時間でも一緒に話す
「聞いてもらえる」「受け止めてもらえる」という安心感が、子どもにとっての心の栄養です。
「今日どうだった?」と聞いても、「べつに」「ふつう」と言われてしまう…。
そんな日もありますが、あきらめずに話しかけることが大切です。
具体的な質問に変えてみるのもコツです。
たとえば…
- 「給食は何が出たの?」
- 「今日、一番楽しかったのはなに?」
- 「席の近くにいるのは誰?」
また、無理に話させようとせず、子どもが話し出すまで待つ姿勢も大切です。
一緒におやつを食べる、夕飯をつくる、絵本を読むなど、自然な関わりの中で少しずつ心を開いてくれます。
④ 「できた!」を一緒に喜ぶ
子どもの“小さな成功”を見逃さず、一緒に笑顔になりましょう。
大人から見たら当たり前のことでも、子どもにとっては大きなチャレンジです。
- 自分でランドセルを片付けた
- 音読を最後まで読めた
- 靴をそろえて脱げた
そんな時こそ、「すごいね!」「一人でできたね!」と声をかけてあげてください。
この“成功体験”の積み重ねが、「ぼく(わたし)はできるんだ」という自信につながります。
否定的な言葉よりも、前向きな言葉をかけてあげるだけで、子どものやる気はぐんと育ちます。
⑤ 困ったときは学校・学童に相談する
“一人で抱えない”ことが、子どもの笑顔にもつながります。
「先生に相談するなんて迷惑かな…」と遠慮してしまう方も多いかもしれません。
でも、学校や学童の先生は、日々たくさんの子どもたちを見ているプロ。
気軽に話してくれることで、学校側も子どもへの対応を考えやすくなります。
たとえば…
- 「家ではこういう様子なんですが、学校ではどうですか?」
- 「朝すごく行き渋るんです。何か学校で困っていないか気になっていて…」
など、率直に伝えてみると安心感につながることが多いです。
また、地域の子育て支援センターや子育て電話相談など、行政のサポートも活用してみましょう。
「誰かに話せる」ことが、親にとっても心のゆとりになります。
必要なときに必要なだけ。
この5つのサポートを、無理なく、少しずつ、日々の生活に取り入れてみてください。
どの家庭でも、小1の壁は「少しずつ越えていける」もの。
親のやさしさと見守りの中で、子どもは確実に成長していきます。応援しています🌸
家庭学習は「遊び感覚」でOK
学習習慣はまず5分から
最初は5分だけ。短く、楽しく、がコツです。
「宿題やった?!」ではなく「今日は何やるの?」と一緒に取り組む姿勢を持ちましょう。
読み聞かせ・カード遊び・生活の中の学び
お風呂で「いちたすいちは?」「牛乳ってどこから来るの?」とクイズ感覚で問いかけてみるのも◎。
勉強=つまらない、にならない工夫が大切です。
体験談:うちの子も乗り越えた「小1の壁」
わが家の長男も、小学校に入った最初の3ヶ月は、帰宅後すぐ寝てしまったり、毎朝「行きたくない」と泣いていました。
わたしも毎朝涙をこらえて「いってらっしゃい」と送り出していたのを覚えています。
でも、ある日、はじめて「友だちができたよ」と笑顔で話してくれました。
少しずつ表情が明るくなり、帰り道もルンルンに。
振り返ると、「大丈夫だよ」「がんばらなくていいよ」と毎日声をかけていたことで、親子ともに少しずつ乗り越えられたのだと思います。
不安なときに頼れるサポート先
学校の担任・保健室の先生
日々子どもを見守ってくれている存在。家庭の状況を伝えるだけでも、安心材料になります。
地域の子育て支援センター
悩みを相談できる専門スタッフや、同じような立場の親御さんと出会えることも。孤独にならずにすみます。
同じ学年の親同士のつながり
参観日や保護者会などでの雑談も大切な情報源です。
「うちも同じよ〜」という一言に救われることもあります。
おわりに:親子でゆっくり成長していこう
「小1の壁」は、決して特別なものではありません。
多くの家庭が、同じような不安を経験しています。
大切なのは、「子どもががんばっているように、親もがんばっている」ということを認めること。
焦らず、無理せず、親子で一歩ずつ。
今日もあなたとお子さんが、穏やかに過ごせますように。
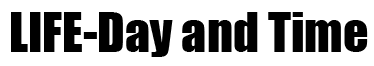



Comment