福銭(ふくせん)を持ち歩くと金運がつく
神社やお祭りなどで授けられる「福銭」を財布に入れておくと、金運が上がるとされます。特に商売人の間で信仰されてきた習慣です。
年末に財布を新調すると翌年の金運が良くなる
年の終わりに財布を買い替えることで、悪い運を断ち切り、新しい金運を呼び込めるとされます。タイミングが大事という点で、風水とも通じる迷信です。
健康・体にまつわる迷信 〜体の声と心のサイン、古人の知恵〜
昔の人々は、体のちょっとした変化や不調に敏感でした。現代の医学とは異なるけれど、日々の暮らしの中で「こんなときはこうすると良い」「これは病の前触れ」といった経験則が迷信として残っているのです。
体を守るため、そして病を防ぐための迷信の数々を、今回は紹介します。
寝る前に髪を乾かさないと風邪をひく
風邪と髪の水気を関連づけた迷信で、冷えと湿気が病気を呼ぶという考え方に基づいています。今でも親が子どもに注意する定番のセリフですね。
くしゃみが2回続くと風邪の兆候、3回なら他人の噂
1回目で体の反応、2回目で体調の前兆、3回目で他人の念──というように、回数によって意味が変わるという迷信が日本では広く知られています。
夜に笛を吹くと病人が出る
これは「夜に音を立てる=死者を呼ぶ」といった霊的な意味も含む迷信。騒音や冷えが病を招くという警告でもあります。
熱が出たときは首の後ろを冷やすと良い
実用的な意味もありますが、「首は気の出入り口」とされる東洋医学の観点からも、冷やすことで悪い気を鎮めるという意味が含まれています。
おへそを出して寝るとお腹を壊す
小さな頃から言われる迷信ですが、実際にお腹が冷えることで腹痛の原因になることも。現実と迷信の境界が曖昧な、生活知の一つです。
食後すぐ寝ると牛になる
子どもへのしつけとして有名な迷信。怠け者=牛という連想で、食べた後すぐに寝ると、体に悪いという教訓がユーモアを交えて語られています。
左のまぶたがピクピクすると良いことがある、右だと悪いことが起こる
体の異変を「吉凶のサイン」として解釈する代表的な例。まぶたの痙攣は東洋でも西洋でも様々な解釈がありますが、左右で意味が分かれるのが特徴的です。
顔に吹き出物ができる場所で、体の不調がわかる
おでこはストレス、あごはホルモンバランス……というように、体のサインが顔に現れるとする民間の迷信。東洋医学の「顔診断」とも通じる考え方です。
爪の白い点は幸運の印
爪に現れる白点は「幸運が近いサイン」とされ、特に薬指や中指に出ると恋愛運や金運が良くなると信じられています。
家・建築・暮らしの迷信 〜住まいは運の入り口、幸運を呼び込む知恵〜
家や暮らしにまつわる迷信は、生活の基盤を守り、安心して暮らすための知恵として受け継がれてきました。
家相(かそう)や風水にも通じる、日々の暮らしの中に根づいた縁起と不吉のサインをまとめてご紹介します。
玄関に鏡を置くと運気が変わる
鏡は「気」を跳ね返すアイテム。玄関に向かって右側に置くと金運、左側に置くと人間関係運が上がるとされます。ただし真正面に置くと運を跳ね返してしまうとされるので注意が必要です。
北枕で寝ると縁起が悪い
仏教の教えに由来し、釈迦が亡くなったときの姿が「北枕」だったことから、「死者の寝方」とされて避けられています。ただし、風水では北枕が良いとされる場合もあり、解釈が分かれます。
家の中心に階段があると家族運が乱れる
家の中心は「気の中心」とされるため、そこに階段などの「動くもの」があると、気が乱れ、家庭内不和や体調不良につながるという家相上の迷信です。
新築や引っ越しのときは「お清めの塩」をまく
新しい住まいに穢れ(けがれ)を持ち込まないように、塩で清めるという風習。日本ではとくに玄関や四隅にまくことが多く、「場を清める」意味合いがあります。
家の西側に水回りがあると金運が落ちる
風水の影響を受けた迷信で、「西=金運の方角」とされ、水は流れてしまう性質があるため、金運が流れるとされます。
台所に包丁を出しっぱなしにすると家運が下がる
刃物は「気を切る」「縁を切る」象徴。包丁を出したままにしておくと、争いや不和が生じやすくなるとされ、台所の清潔と秩序が重視されます。
縁側に猫が来ると幸運が訪れる
古い日本家屋で語られる縁起の良い話。猫は福を呼ぶ動物とされており、特に縁側や庭にふらりと現れる猫は「良いことの前兆」とされました。
引っ越しのときに雨が降ると縁起が良い
意外にも「雨降って地固まる」として、引っ越し当日の雨は「良いスタートのしるし」とされます。ただし、地域や家系によっては逆に「水に流れる」として嫌うことも。
家の角に植物を置くと気が安定する
風水にも通じる考えで、家の「角」は気がぶつかりやすい場所とされます。そこに観葉植物を置くことで、気の流れを柔らかく整えると信じられています。
雨戸を閉め忘れると運が逃げる
日本の伝統家屋では「雨戸を閉める=家を守る」意味があり、閉め忘れると外の邪気や不運が入り込むとされます。災害時の備えとしても、生活習慣として定着しています。
節分に玄関にイワシの頭とヒイラギを飾ると邪気が入らない
節分に家の入口にイワシの頭をヒイラギの枝に刺して飾る風習。「匂いとトゲ」で鬼を寄せつけないという、見た目も匂いもインパクトのある魔除けです。
トイレのふたを開けっぱなしにすると運気が下がる
トイレは「陰の気」が強い場所とされており、ふたを開けたままにしておくと、家全体の運気が下がると信じられています。清潔と密閉がカギです。
朝、玄関を掃除すると運気が入ってくる
玄関は「運気の通り道」とされ、朝に掃き清めることで、良い気が入り込みやすくなるとされます。逆に夜の掃除は「運を掃き出す」とされる場合も。
食べ物に関する迷信 〜口に入るものには、神も魔も宿る〜
食べることは生きること。だからこそ、昔の人々は食べ物に特別な意味や信仰を込めてきました。
食材や食事の仕方にまつわる迷信の中には、健康、運、災い、そして縁を左右すると言われるものまでさまざま。ここでは、食にまつわる不思議な言い伝えやジンクスを紹介していきます。
茶柱が立つと縁起が良い
お茶を注いだときに、茶柱がピンと立って浮かぶと、「良いことが起きる」「願いが叶う」とされます。珍しい現象であるため、偶然の中に意味を見出す日本人の感性が表れています。
食べてすぐ横になると牛になる
子どもに向けたしつけの定番。食後すぐに寝転がることは消化不良のもとになり、健康に悪いという教訓が、動物にたとえて面白おかしく伝えられました。
おにぎりは三角に握ると魔除けになる
三角形は山を象徴し、神聖な形とされました。山=神が宿る場所という日本の信仰が背景にあり、旅や仕事のお供としてのおにぎりは、神の加護を受ける食べ物だったのです。
朝ごはんを抜くと運が逃げる
「朝の行動が一日を決める」という考えから、朝ごはんをしっかり食べないと運気が入ってこないとされました。仕事運や学業運を気にする家庭では、特に重要視されてきた迷信です。
赤い食べ物は厄除けになる
赤は生命力や魔除けの色とされ、梅干しや唐辛子など赤い食材を食べることで体を守ると信じられてきました。正月や祝い事に赤い料理が多いのもこの信仰によるものです。
お正月に黒豆を食べると「まめに働ける」
「まめ=健康・勤勉・努力」を意味し、黒豆を食べることで新年の健康と労働への意欲を祈るという、縁起かつぎの代表的な迷信です。
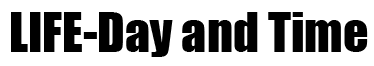


Comment