和の美意識を映す「和を感じる言葉」を通じて、日本美や季節感に満ちた雅語の世界をご紹介します。古来より大切にされてきた自然や風流、幽玄の情緒を感じることで、日常にほんのひとときの安らぎと彩りを添えてみませんか?
ここでは、四季折々の風景や心の機微を表す100の雅語を厳選し、カテゴリー別にわかりやすく解説します。
和を感じる言葉 一覧
※本記事の名称、説明文には一部、造語など架空の単語が含まれています。意味については辞書等でご確認ください。
【自然・四季の美】
- 雪月花(せつげつか)
雪・月・花の自然の美を愛でる心。四季折々の風景に心を寄せる日本人の美意識。 - 花鳥風月(かちょうふうげつ)
花や鳥、風や月といった自然の情景を鑑賞し、風流を楽しむ心を表す言葉。 - 山紫水明(さんしすいめい)
山が紫にかすみ、水が清らかに輝く、美しく澄んだ自然の景観を賞賛する語。 - 風光明媚(ふうこうめいび)
自然の景色が非常に美しく、眺めて心が洗われるような場所を称える表現。 - 春夏秋冬(しゅんかしゅうとう)
一年を通じた四季の移ろい。季節ごとの風情を大切にする心を表している。 - 松風水月(しょうふうすいげつ)
松を吹く風と水に映る月、自然界の清らかさと静謐さを讃える美的表現。 - 月白風清(げっぱくふうせい)
月の光が白く澄み、風が清らかに吹く、凛として気高い夜の美を表す。 - 朝露晩霜(ちょうろばんそう)
朝の露や夜の霜のように、一瞬の美や厳しさを象徴する季節の変化の描写。 - 雲外蒼天(うんがいそうてん)
困難を乗り越えれば、青空のように希望と安らぎが待つという教訓の語。 - 錦上添花(きんじょうてんか)
すでに美しいものに、さらに美しさを加える様子。完成された風雅の象徴。
【風流・趣きのある語】
- 風流韻事(ふうりゅういんじ)
風情ある生活や趣味を楽しむこと。詩歌や茶の湯など雅な文化を表す語。 - 琴瑟相和(きんしつそうわ)
夫婦仲が睦まじいこと。琴と瑟の音色が調和するような理想的関係のたとえ。 - 絢爛豪華(けんらんごうか)
色や装飾が華やかで輝きに満ちた、視覚的に極めて美しい様子を表す。 - 虚心坦懐(きょしんたんかい)
先入観なく、素直で偏りのない心持ち。心を空にして物事に向き合う姿勢。 - 詩情豊潤(しじょうほうじゅん)
詩的な感性が豊かで、情緒に満ちた心のあり方。芸術や文学に通じる心。 - 紅炉点雪(こうろてんせつ)
熱い炉に雪が落ちてすぐに消える様子。真理や悟りに至る速さのたとえ。 - 青山緑水(せいざんりょくすい)
青く茂った山と緑の水辺。大自然の美しさや落ち着いた風景を意味する。 - 悠々閑々(ゆうゆうかんかん)
ゆったりとしていて心静かであるさま。慌ただしさと無縁の精神状態。 - 花紅柳緑(かこうりゅうりょく)
花が紅く、柳が緑に揺れる春の自然。まさにこの世の色彩の美の極み。 - 浮世絵巻(うきよえまき)
人々の暮らしや世相を絵巻物のように描いた言葉。移ろう時代の映し鏡。
【幽玄・静寂・心の奥行き】
- 幽玄(ゆうげん)
目には見えぬ奥深い美。静けさや余白の中にこそ宿る、日本独自の美意識。 - 物の哀れ(もののあわれ)
儚さや無常に心を動かされる感受性。古典文学の根底に流れる情緒の本質。 - 寂寥感(せきりょうかん)
物静かでわびしいが、そこに心の奥行きと余韻がある繊細な感情を示す。 - 余情残心(よじょうざんしん)
あえて語りきらず余韻を残す美学。和の芸術や文学に見られる美の姿勢。 - 無為自然(むいしぜん)
作為を排し、自然のままにあることを尊ぶ思想。老荘や禅に通じる理念。 - 心頭滅却(しんとうめっきゃく)
心を空にすれば火もまた涼し。外の苦しみに心を惑わされぬ境地を指す。 - 玉響(たまゆら)
ごく短い時間やかすかな響き。極めて繊細な美や命の儚さを表す古語。 - 一期一会(いちごいちえ)
一生に一度の出会いを大切にする茶道の教え。今この瞬間を全力で生きる心。 - 夢幻泡影(むげんほうよう)
人生の無常を表す仏教語。夢や泡のように儚いこの世の在り様を示す。 - 静寂無言(せいじゃくむごん)
静けさと沈黙の中にこそ、真の意味や感動が潜むという精神世界の象徴。
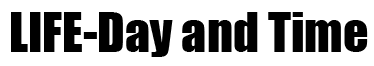



Comment